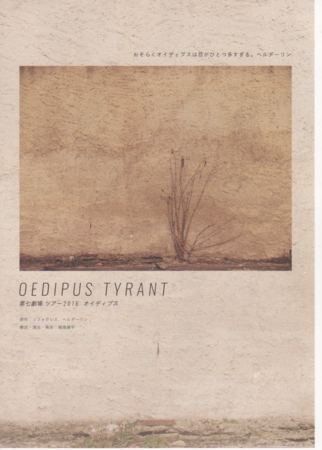第七劇場『オイディプス』
オイディプスを嗤えるか
原作:ソフォクレス、ヘルダーリン
構成・演出・美術・訳:鳴海康平
文・ 小谷彩智

第七劇場 ツアー2016『オイディプス』京都公演 撮影:第七劇場
何をもって悲劇とするのか。この戯曲を前にそのような問いを持つこと自体今更だと言われてしまいそうであるが、今、舞台を目の前にする観客である私たちは、そのことについて何度でも思いをめぐらす意義がある。
現在を、生身の人間として生きる私たちにとって、最も現実的な悲劇感覚とは。
この度、第七劇場の『オイディプス』を観劇するにあたり、改めてその原作戯曲を読み返してみた。
古代ギリシャ、テバイの国。先王亡き後、その妻イオカステを娶り国を治めていたオイディプスは、滅びゆく国を救うため、災いの根源である先王殺害の犯人を突き止め、罰するよう神託を受けるが、実はその犯人は自分であり、なおかつ妻とした女性は自分の母親であったという悲劇的物語である。
私自身が十数年ぶりに再読したというのもあるが、その戯曲構造、セリフひとつ、言葉ひとつにおいても、こんなにも熱量がこめられているものだからこそ残り続けている戯曲なのだというのを第一に再確認した。例として、すでに序盤で真実を告げることをためらう預言者テイレシアスに対し、執拗に迫り、挙句の果てには怒りにまかせてこの預言者を犯人の一味だとまで揶揄するやりとりは、オイディプスの無邪気さゆえの高慢な執着心を見せつけるには余るほどの言葉の応酬であり、その言葉を発する彼自身の危うさやその後の運命の行く末を予想させるには充分なほどの不穏さと激しさだ。
さて、何度も何度も様々な形で表現されてきたであろうこの戯曲を元に、今回はどのような舞台作品が上演されるのか。特に演出面において我々は、新しさを求めるが故に、時として過剰な裏切りを期待してしまいがちだ。しかし、今回の舞台に私はそれほどの「裏切り」を感じなかった。と、言ってしまうとつまらないようだが、逆である。
舞台には壁に沿って物が配置されている。扉の破片、ひしゃげた拡声器、数冊の本、あれは何だろうか、ダクトの一部か。それらが白で統一した空間に配置され、博物館の展示物のようだ。
このようなシンプルな舞台装置における抽象的表現は時として象徴的になりすぎてしまい、あたかも『そこから何かを感じ取らないといけない』という義務感が生じる為あまり好まないのだが、今回のこの「展示物」たちは抽象的な何かではなく、純粋に「舞台美術」としての立ち位置を弁えた存在感であり、空間になじみ、独特の空気をそこでつくりあげる役目を果たしていた。陳列されている物たちの存在感はそれはど強くはないが、「展示」されることによって、時の経過が感じられ、観客と舞台との距離感をかもしだす。この距離感が客席に座る我々に何かが起こりそうだと想像させる余白を与えている。
第七劇場 ツアー2016『オイディプス』三重公演 撮影:西岡真一 では実際そこで演じられた作品についてはどうか。白い空間に対し、黒いスーツや現代の衣服を着た役者が発するセリフのひとつひとつは膨大な熱量をもって、原作戯曲に忠実に発せられるのに対し、オイディプスとその他の登場人物たちとのやりとりにこめられた感情には一種の距離感が在った。先に述べたように戯曲を読んだ段階では、個人の解釈もあるだろうが、その物語やセリフの激しさから、個々の登場人物が人間くさく、出来事に直面する彼らの行動にも感情的な観点から、読者はある種「共感」を持つだろうし、全体のドラマ性にも感服するだろう。読み継がれ、上演され続けている理由がそこにあるとすれば、今回の舞台に存在する「距離感」とは。
では実際そこで演じられた作品についてはどうか。白い空間に対し、黒いスーツや現代の衣服を着た役者が発するセリフのひとつひとつは膨大な熱量をもって、原作戯曲に忠実に発せられるのに対し、オイディプスとその他の登場人物たちとのやりとりにこめられた感情には一種の距離感が在った。先に述べたように戯曲を読んだ段階では、個人の解釈もあるだろうが、その物語やセリフの激しさから、個々の登場人物が人間くさく、出来事に直面する彼らの行動にも感情的な観点から、読者はある種「共感」を持つだろうし、全体のドラマ性にも感服するだろう。読み継がれ、上演され続けている理由がそこにあるとすれば、今回の舞台に存在する「距離感」とは。
オイディプスの持つ感情は人間の内に生じ得る普遍的、根源的な猜疑心や恐怖心、怒りや悲しみ、絶望、といったものである。その自己に起こる出来事にふりまわされる彼をテイレシアスは預言者として、あえて真実を語らないことによって導こうとする。それは人間の、破滅から逃れ生きようとする処世だ。一見これは自身にとっても相手にとっても、人情味のある反応に思える。しかし実際の上演でテイレシアスは、博物館の作品解説を一方的に読み上げるように話し、その態度はオイディプスに関わろうとしないかのようだった。イオカステもただ悲劇の成り行きの中に置かれる女性ではなくオイディプスの激情にわずかな距離を取り、抵抗感や非難性を持った語気でセリフを語る。
オイディプスは、叔父であり義弟でもあるクレオンさえも先王殺害の犯人と疑い、「追放ではすまされぬ。わしののぞむのは、お前の死だ。」とまで言い切る。そうした目にあわされながらも、クレオンは破滅していくオイディプスに対し、最後に娘たちとの面会を叶え、安らかな生活へと戻すように館へ導いてやる。そのクレオンも、黒くスタイリッシュなスーツと現代風にセットされた髪型というなりで登場し、オイディプスの背中からのしかかるような不吉な動きで彼に重圧を与え、会話の所々で冷やかなまなざしをあびせる。心の底では誰も信用しておらず、身内さえも簡単に切り捨ててしまうような危なっかしさを感じた。
第七劇場 ツアー2016『オイディプス』京都公演 撮影:第七劇場
 オイディプスを取り巻くこれらの人物たちの行動は、観客と舞台空間との間にある「余白」をただならぬ不安感に変えた。セリフはテキストには忠実ながらも、読み取れる登場人物の人間味を演技でもって薄めている。ここにある落差こそがこの舞台に常に存在している距離感ではないだろうか。観客が自身を重ねて物語全体の悲劇性を感じとる場合、オイディプスに対しては少しばかりの憐れみと蔑みの念を抱くだろう。真実を知りたいが故に根拠もなく周りの人間を疑ってかかるような「オイデ ィプスの利己的な部分」をどこかで責める気持ちが生まれるはずである。己の目を潰し、痛い、痛いとのたうちまわる姿を嘲笑うかのようなニュアンスを含んだクレオンの態度も妙に現実的でヒヤリとさせられた。
オイディプスを取り巻くこれらの人物たちの行動は、観客と舞台空間との間にある「余白」をただならぬ不安感に変えた。セリフはテキストには忠実ながらも、読み取れる登場人物の人間味を演技でもって薄めている。ここにある落差こそがこの舞台に常に存在している距離感ではないだろうか。観客が自身を重ねて物語全体の悲劇性を感じとる場合、オイディプスに対しては少しばかりの憐れみと蔑みの念を抱くだろう。真実を知りたいが故に根拠もなく周りの人間を疑ってかかるような「オイデ ィプスの利己的な部分」をどこかで責める気持ちが生まれるはずである。己の目を潰し、痛い、痛いとのたうちまわる姿を嘲笑うかのようなニュアンスを含んだクレオンの態度も妙に現実的でヒヤリとさせられた。
物語の悲劇性にカタルシスを得て終わってしまうのではなく、演劇の持つ一種幻想的なフィクション性と、生身の人間によって演じられるものだという現実性の間でより現実の側に立った演技が追求されていた。強制的に意識を分断するようなノイズと共に切り替わる場面、不意に点く蛍光灯の白々しさが幻想へと観客を逃してくれない。観る側にあれこれと思考する隙を与えず、観客演者隔てなくそこに居るものの「感覚」を刺激してくる。
ここではないどこかへ自分を追放してくれ、殺してくれと嘆くものの望みを叶えず、その手を引いて館に返してしまうのも充分に悲劇的だと原作を読んだ段階で思ったが、犯した罪を罪として冷やかに、博物館で観る物のように、過ぎ去った時代のものとして静観されてしまうのが真に悲劇的であり絶望的ではないか。オイディプスはこんなにも舞台に存在したというのに。
「わたしたち一人ひとりが傲慢の狭い塔の中に留まり、小さい窓に向かってめいめいに喚くようになって、もうずいぶんと時間が経っているようです。」この戯曲を選んだ時点で演出の鳴海氏は、はなからそんなことは望んではないだろうが、古典を再現し古代人との共通点を見つけることになど表現の意義を求めておらず、むしろ人間の持つ感情を前提としたうえで、個の細部を際立たせることによって、狭まってしまった我々の「感覚」のあり方を穿り出されるような舞台であった。
(2016年6月2日掲載)
第七劇場 ツアー2016『オイディプス』三重公演 撮影:第七劇場
小谷彩智
劇作家。近畿大学芸術学科演劇芸能専攻卒。大学では主に役者として演技について学ぶ。母校である鴨沂高校の校舎建替問題を題材に執筆した「S.」が2014年京都演劇フェスティバルで上演された。
劇場間提携プログラム|第七劇場
『オイディプス』
原作:ソフォクレス、ヘルダーリン
構成・演出・美術・訳:鳴海康平
出演
小菅紘史・伊吹卓光・菊原真結
米谷よう子・峰松智弘・川田章子
佐々木舞・堀井和也
日程
2016年5月20日(金)~22日(日)
5月20日(金)19:30
5月21日(土)15:00 / 19:30
5月22日(日)15:00
ー「おそらくオイディプスは目がひとつ多すぎる」ヘルダーリン
真実は常に善ではなく、すべてを明かそうという欲望は暴力にもなり、その傲慢は罪にもなる。今から約2500年前に書かれ、西欧演劇の原点であるギリシア悲劇の最高傑作『オイディプス王』。災厄に苦しむ国の王が直面する父と母との苛酷な運命を描いた物語。2015年4月、早稲田大学・早稲田小劇場どらま館開館記念事業で初演。三重・京都・金沢・岡山を巡る新演出版ツアー公演。