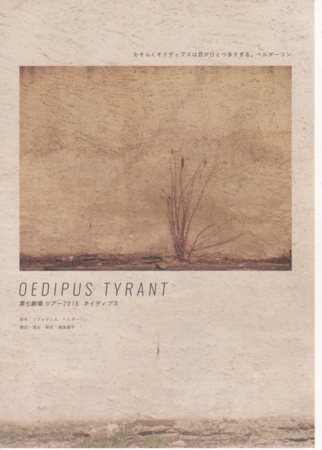第七劇場『オイディプス』
原作:ソフォクレス、ヘルダーリン
構成・演出・美術・訳:鳴海康平
文・野村明里

第七劇場 ツアー2016『オイディプス』三重公演 撮影:松原豊
数多くの神話の中でも、ギリシア悲劇の最高傑作として今日でも読み継がれる戯曲、ソフォクレスの『オイディプス王』。古代ギリシアでは自然は(現在もそうであるように)畏怖すべき対象であり、脅威であった。そして、自然がもたらす危機や災厄に対する先人たちの知恵を伝承するために、「神話」が生まれた。
19世紀初頭、啓蒙主義が広がるヨーロッパにおいて、ドイツの詩人ヘルダーリンは当時の人々の人間性の退廃を危惧し、かつての古代ギリシアに希望を見ていた。彼は、近代化・文明化によって自然をも我が物にしてしまおうとする人間の傲慢さを嘆いていた。ヘルダーリンの世界には神が満ち満ちている。それらはキリスト教の神ではなく、ギリシア神話の神々である。絶対的な一神教ではなく、多神教の世界である。彼を惹きつけてやまなかったのは、ギリシア古典の世界の豊饒な自然に根差した生命力と美であった。
第七劇場 ツアー2016『オイディプス』三重公演 撮影:松原豊 第七劇場『オイディプス』は、ヘルダーリンの独語訳を基に、演出の鳴海康平が日本語訳を行ったテキストが用いられている。そのあらすじは以下のようなものである。先王ライオス亡き後、オイディプスはスフィンクスを打ち倒し、テバイの王となる。しかし、オイディプスが王になって以来、テバイでは不作と疫病が続く。オイディプスは神へ神託を求めたところ、「この国から恥辱を払え」との神託を受け、すぐに殺害犯の捜索に当たる。その過程で自らの出生の秘密と、自分がその殺害犯であること、さらに妻イオカステは自分の母であったことを知り、自ら自分の目を潰し、王位を退く。
第七劇場『オイディプス』は、ヘルダーリンの独語訳を基に、演出の鳴海康平が日本語訳を行ったテキストが用いられている。そのあらすじは以下のようなものである。先王ライオス亡き後、オイディプスはスフィンクスを打ち倒し、テバイの王となる。しかし、オイディプスが王になって以来、テバイでは不作と疫病が続く。オイディプスは神へ神託を求めたところ、「この国から恥辱を払え」との神託を受け、すぐに殺害犯の捜索に当たる。その過程で自らの出生の秘密と、自分がその殺害犯であること、さらに妻イオカステは自分の母であったことを知り、自ら自分の目を潰し、王位を退く。
舞台上には、古い拡声器や扉の欠片のようなもの、本、何か管状の物体などが壁に沿って等間隔に展示されており、まるで博物館か美術館のようである。舞台上手には机と数脚の椅子が置かれている。そこにコロス役(川田章子・佐々木舞)の俳優が入ってきて、展示品を鑑賞する。一人は監視員のように傍観している。そして彼女らがヘルダーリンの詩「ムネーモシュネー(記憶の女神)」を、歌うような独特の口調で朗読するところから劇が始まる。アキレウス、アイアス、パトロクロス…、詩の後半部では非業の死を遂げたギリシア古代の英雄たちの名が次々に唱えられ、これから始まる大きな悲劇を予感させる。
現代的な衣装を纏った俳優達が現れ、何も見たくはないとでもいうように自らの手で顔を覆う。スーツ姿のオイディプス(小菅紘史)の腕を他の俳優が掴んだり、目を覆ったりするが、オイディプスはそれを振り払い、時折天を仰ぐようなしぐさを見せる。舞台奥のスクリーンにはスクランブル交差点や都会の街並みの映像が映し出され、古代ギリシアと現代のイメージがオーバーラップする。
シーンのほとんどは目の冴えるような均一な蛍光灯の下で進み、床の白さのせいもあってか一面に白く、会議室か病院か学校のPC室のような冷めた印象を受ける。劇はほぼ原作通りの筋書きと台詞によって進行し、所々でコロスによるヘルダーリンの詩の朗読が挿入される。それぞれの俳優の身体性は研ぎ澄まされ、語られる言葉にもエネルギーがあるのだが、彼らは互いにほとんど視線を合わせることがなく、交わす台詞はまるで独白の応酬のようで、対話として噛み合うことがない。その距離感には一種の違和を感じる。
冒頭、「この国から恥辱を払え」という予言の神アポロンからの神託を聞いたオイディプスは、その神託と先王ライオスの死とを結び付け、その事件を「罪」と捉えて早急な犯人探しを始める。これに続く場面はほとんどすべて、何もかもの真実を知ろうとするオイディプスの格闘である。物語の序盤、盲目の預言者テイレシアス(米谷よう子)が彼女の良心から先王殺害についての真実を告げることを躊躇する場面では、オイディプスは未知から生まれる怒りに任せ、傲慢な態度と強い語気で追究し続ける。その知的好奇心は熱狂的であり、オイディプス自身が捉えうる以上のものを何がなんでも知ろうとするその姿は、いささか狂気を孕んでいる。
特筆したいのは、シーンの区切りや劇中に唐突に訪れる転換についてである。基本的には細かなシーンの変わり目に暗転・明転がある。前シーンの余韻を残すことなく機械的にカットアウトしてしまうので、物語世界に没入することができない。さらに、劇の中盤、オイディプスとイオカステ(菊原真結)の会話によってオイディプスの真実の過去がだんだんと明るみになっていく場面においては、短いスパンで不規則的に暗転・明転する。「(イオカステ)……ありませんでした。●暗転●だからあなたも、予言者の言うことなど▲明転▲気にかける……」といった具合であり、台詞の途中であろうとお構いなしである。暗転中は台詞だけが聞こえてくる。数秒間の暗転後、明転すると俳優が移動していたり向きを変えていたりするので、気になってじっと見つめてみる。しかしそこにはただ暗闇があるばかりである。気が散って台詞も部分的にしか頭に入ってこない。「これ以上は見るな」と言わんばかりに強制的に、観客は一時的な盲目状態にさせられるのである。
第七劇場 ツアー2016『オイディプス』京都公演 撮影:第七劇場
 先にも述べたように、物語の終盤、すべての真実を知ったオイディプスは自らの手によって盲目となる。長い暗転状態に陥り、轟音とオイディプスの悲痛な叫び声が劇場内を支配する。暫くして赤い光によって照らされる舞台は、目から流れる鮮血を通してみる世界のようでもある。その後何事もなかったかのように明転し、蛍光灯の光と穏やかな音楽の中、オイディプスは二人の娘と最後の挨拶を交わすが、クレオン(伊吹卓光)によって無情にも引き離される。そしてひとり舞台の隅で柔らかな光に照らされうずくまるオイディプスの姿は、博物館の展示物の一つのようであった。
先にも述べたように、物語の終盤、すべての真実を知ったオイディプスは自らの手によって盲目となる。長い暗転状態に陥り、轟音とオイディプスの悲痛な叫び声が劇場内を支配する。暫くして赤い光によって照らされる舞台は、目から流れる鮮血を通してみる世界のようでもある。その後何事もなかったかのように明転し、蛍光灯の光と穏やかな音楽の中、オイディプスは二人の娘と最後の挨拶を交わすが、クレオン(伊吹卓光)によって無情にも引き離される。そしてひとり舞台の隅で柔らかな光に照らされうずくまるオイディプスの姿は、博物館の展示物の一つのようであった。
この悲劇の主題は、父殺しでも近親相姦でもなければ、自分探しでもない。公演パンフレットに記載されているヘルダーリンの「おそらくオイディプスは目がひとつ多すぎる」という言葉にも象徴されるように、すべてを見ようとすること、「すべてを知ろうとする人間の傲慢さ」にあるのだ。かつてヘルダーリンは、啓蒙主義によって文明化が進み傲慢になっていくギリシア人たちの状況を嘆いた。今、鳴海康平はそのことを現代人に問いかけている。
しかしながら、「すべてを明かそうという欲望は暴力にもなり、その傲慢は罪にもなる」という一つの真実を、(暗転状態によって一時的に盲目になるとはいえ)舞台上の潔白な蛍光灯の下で赤裸々に明るみにするのは罪にはならないのか。まさか、芸術だけは特権的であるとは言わせまい。
(2016年6月30日掲載)

第七劇場 ツアー2016『オイディプス』三重公演 撮影:松原豊
野村明里
俳優。同志社大学文学部美学芸術学科卒。在学中より映像・舞台問わずフリーで活動。
主な出演作に、京都芸術センター演劇計画Ⅱ『新・内山』、
2016年アトリエ劇研スプリングフェス参加作品:居留守『ベルナルダ家』等。
劇場間提携プログラム|第七劇場
『オイディプス』
原作:ソフォクレス、ヘルダーリン
構成・演出・美術・訳:鳴海康平
出演
小菅紘史・伊吹卓光・菊原真結
米谷よう子・峰松智弘・川田章子
佐々木舞・堀井和也
日程
2016年5月20日(金)~22日(日)
5月20日(金)19:30
5月21日(土)15:00 / 19:30
5月22日(日)15:00
ー「おそらくオイディプスは目がひとつ多すぎる」ヘルダーリン
真実は常に善ではなく、すべてを明かそうという欲望は暴力にもなり、その傲慢は罪にもなる。今から約2500年前に書かれ、西欧演劇の原点であるギリシア悲劇の最高傑作『オイディプス王』。災厄に苦しむ国の王が直面する父と母との苛酷な運命を描いた物語。2015年4月、早稲田大学・早稲田小劇場どらま館開館記念事業で初演。三重・京都・金沢・岡山を巡る新演出版ツアー公演。